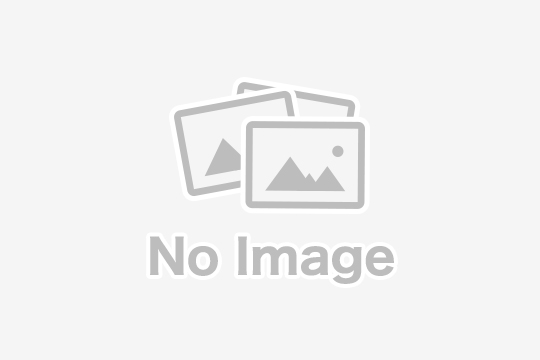WEBサイトを立ち上げたものの、「何から始めればいいのか分からない」と悩んでいる方や、すでに運用しているものの「効果がイマイチ実感できない」と感じている方は少なくないでしょう。実際、多くの企業や個人が、WEBサイトを持つことの重要性を理解している一方で、どのように効果的に運用するかについては悩みが尽きません。
あなたのWEBサイトは、単なる情報発信の場ではなく、ビジネスやブランドの顔とも言える存在です。適切なマーケティング戦略を用いなければ、せっかくの資産も活かしきれず、時間やコストが無駄になってしまうかもしれません。この記事では、マーケティングの視点からWEBサイト運用を成功に導くために意識すべきポイントについて探っていきます。あなたのWEBサイトを本当に機能させるための第一歩を、一緒に考えていきましょう。
※本記事で解説する「WEBサイト」には、ドメイン配下にブログ機能も備えたサイトを想定しているため、コーポレートサイトとしての機能だけでなく、コンテンツマーケティング全般に通ずる話も展開しています。
起点にするイシューを設定する
イシューとは、日本語で「論点」「課題」「問題」などと訳されることが多い言葉です。しかし、単なる問題点だけでなく、解決することでより良い状況へ導く可能性を秘めた課題という意味合いが強い点が特徴です。 Geminiより
ざっくりというと「問題や課題に見えるもの」であったり「問題や課題を定義するための論点」など、問題・課題に付随するあらゆる要素を内包する概念がイシュー…と考えると掴みやすいでしょう。
したがって「当初はイシューだと思えていたものが大した問題でなくなった」「プロジェクトを進める中で重大なイシューが発見され大幅に進行を見直すこととなった」といった状態が生じる性質を持つものだと考えてください。
イシューに関する定義は、ベストセラー「イシューからはじめよ」を参考に。
「解決することでより良い状況へ導く可能性を秘めた課題」を特定するためには
- 数ある問題点の中でも優先度の高い問題か?
- 一つの課題を解決すことで他の課題もスムーズに解決するか?
- アウトプットに大きな意味をもたらすことができるか?
といった要素を満たすほど良いです。
なぜなら、そのイシューを解決することで、雪だるま式に他の問題も解決する可能性が高い…つまり、一つの問題を解決するだけで他の業務も大幅に効率化できたり、無駄な迷いに時間をかけることなく意思決定をスムーズにできるからです。
では、マーケティング目的でWEBサイトの制作や運用を行うにあたり、重要すべきイシューは何か?
私自身の経験則から踏まえると、下記の4つのイシューを設定できていない事例が非常に多いと感じます。
- ブランディング
- 集客チャネル確保
- CV獲得
- 話題性や時事性
それぞれをイシューとして設定し、思考を深堀りをしていきましょう。
ブランディングを起点とする
ここでいう「ブランディング」とは、「企業、または提供するサービス/プロダクトの知名度や好感度が上げる行為」ぐらいのレベル感をイメージしてもらえれば良いかと思います。
後述する「集客チャネル確保」「CV獲得」をイシューとして考慮していない場合、多くのWEBサイト制作者・運用者が無自覚に「ブランディング」を起点のイシューとして運用している印象にあります。
私が受けるWEB集客の相談でも「問い合わせが欲しいのにブランディング起点のサイト制作をしている」という状態になっていることが、非常に多いです。
では「WEBサイト制作を行うにあたり、最初にブランディングを起点にするべきなのか?」という問いについて考えてみましょう。
下記のような要件に当てはまる場合は、ブランディングを起点にWEBサイト制作を始めたほうがいいでしょう。
- 事業、もしくはサービス/プロダクトの知名度が既に高くイメージ形成されている
- 顧客/市場に伝えたいメッセージやコンセプトが最優先される
- 信頼性が問われやすい商材性質である(BtoB商材、高単価商材など)
マス広告媒体などで知名度が高いサービス/プロダクトであれば、ブランディング起点で制作したWEBサイトであっても、指名検索でアクセス数を確保しやすいです。
また、顧客単価の高い商材を扱う事業(保険や金融など)であったり、誠実なイメージが決め手になりやすいBtoB商材であれば、やはりブランディング起点が良いでしょう。
逆説的に「知名度が低く目先の問い合わせ数確保が課題となる新規事業や小規模企業、個人業者」「信頼性よりも需要が購買の決め手になりやすいBtoC商材」であれば、ブランディング起点でなくても良いかもしれません。
※ここで理由がわからない方は、後のイシューで浮き彫りになるかと思います。
なお、当サイトは「顧客/市場に伝えたいメッセージやコンセプトが最優先」というイシューを起点にし、サイト制作が始まっています。アクセス数確保やCV獲得よりも、読者や市場に伝えたいメッセージが最優先されるからです。
集客チャネル確保を起点とする
集客チャネルとは?
集客チャネルとは、企業が顧客を引きつけ、自社の商品やサービスに興味を持ってもらうために利用する媒体や経路のことを指します。 Geminiより
ここでは「集客チャネル」と大層な言葉を使ってますが、噛み砕いて「アクセス数/PV数が欲しい」と言い換えてしまってもいいでしょう。
WEB集客において、最も多い相談の一つです。
とくによくある例が「WEB制作会社にサイトを作ってもらったけど、アクセス数が全然増えない…」といった課題を抱えた方からのご相談です。
どれだけ良いWEBサイトを作ったところで、集客施策を行ってなければアクセス数は増えません。
(WEBサイトが初期状態でSEO対策されていて指名検索のより微弱なアクセス数を確保できている…といったことは見受けられますが、一般的なWEB制作会社のスコープですと、集客経路を考慮していないことがほとんどの印象です)
さて、集客チャネル確保をイシューにした際の問いですが「どの集客チャネルを選ぶか?」にすべてがかかっていると言ってもいいでしょう。
しかし、シンプルな問いに見えて、決断し切れてない場合も多く感じます。
たとえば「複数以上の集客チャネルを選んだ際に、どちらの集客チャネルにリソースを割くか?」「効果が出るまで時間のかかる集客チャネル確保は、どの期間でどのぐらいのアクセス数が目安か?」といった深堀りができていないようなケースです。
こうした場合、目先のアクセス数の推移に振り回され「どの集客チャネルにもリソースを集中し切れず、アクセス数を確保できない…」という結果に終わります。
また、最低限のアクセス数を確保できないと、解析ツールを使用したPDCAサイクルの遂行に取り組めないという問題も生じます。十分な母数が確保できていないと、定数指標の評価であったり、仮説検証すらできないためです。
雑にまとめてしまえば「どの集客チャネルにどれぐらいの割合でリソース投下し、どれぐらいの期間でどれだけの数値目標を達成するか。撤退ラインはどうするか?」だけ決めてしまえば、集客チャネルを起点としたイシューはスムーズに解消できます。
あとはWEB記事や広告出稿といった「生産活動に集中する状態」を作ってしまえばいいだけなのですから。同時に「生産したアウトプットをいつ、どのような基準で評価するか?」も設定しておきます。
そうすることで、不要なタイミングで「このアウトプットは良くない、結果が出ないんじゃないか?」といった指摘に振り回されることなく、(少なからずそのタイミングでは)重要でないイシューに気を取られることがなくなるからです。
CV獲得を起点とする
CV(コンバージョン)とは?
CV(コンバージョン)とは、Webマーケティングにおいて、ユーザーがWebサイト上で特定の行動を起こしたことを指します。この「特定の行動」は、Webサイトの目的に応じて様々です。 Geminiより
コンバージョンの定義はサイトや取り扱い商材の性質に異なります。
ECサイトであれば「商品の購入」、サービスを提供している事業者であれば「問い合わせ/資料請求/無料体験申し込み」、個人で活動しているなら「メールマガジン登録(顧客リスト確保)/SNSフォロー」などが代表的でしょう。
このCV獲得ですが、WEBサイトでの売上確保が最優先となる事業者にとって最優先イシューとなるでしょう。
とくに組織内での営業力が弱く課題があったり、そもそも営業するリソースが確保できない小規模事業者にとっては「設置して待つだけで問い合わせがくる自動販売機」のようなもの。喉から手が出るほど欲しい、まさに”夢の集客装置”です。
2020年前後、コロナ禍によるリモートワーク環境の増加に伴い「フィールドセールスが行えないため、WEB集客によるリード獲得したい」という意図で、WEB集客を行う企業が増えた印象にあります。
二元論的に語るなら、ブランディングに成功していない事業者、もしくはブランディングにリソースを割けない事業者は、CV獲得を最大イシューとしてWEBサイト制作を行うべきです。
なぜなら、顧客の問い合わせや購買がなければニーズも特定できませんし、営業力のない会社であれば売上すら確保できないからです。
一方でCV獲得のみに注力しすぎると、中身のないWEB記事にバナー広告を表示して無理やりCV導線を敷いたり、押し売りのような訴求をせざるを得ないなどの問題も生じます。
また、CV後に顧客対応が生じる性質のサービスでは、問い合わせ後の業務負担が生じることもある点にも注意が必要です。このことにより、いわゆる「CPA(Cost Per Acquisition-顧客獲得単価)」増加要因ともなります。
WEB集客においては「とにかくCV数を取ってくれ!」という要求も多いですが、以上のように「CVを取った後」についても考慮しなければ問題が発生することも多いため、クライエントへの説明や意思決定への関与についても”繊細さ”が要されるイシューです。
ですので、長期的な事業継続性を考慮するならCV獲得する前にCV獲得しても十分な基盤を整えておくほうが、結果としてコストも安く済みます。
ただ現実として「CV獲得しすぎた際の問題やリスクを経験したことがある人自体が少数派」という背景からも、十分に理解されにくい問題とも言えるでしょう。
話題性や時事性を起点とする
最後に「話題性/時事性をイシューとする」という視点も紹介したいと思います。
話題性や時事性のあるWebサイトは、日々変化する世の中の出来事やトレンドをいち早く捉え、読者の興味を引くようなコンテンツを提供しているサイトです。
具体的な例としては、
- 総合ニュースサイト: Yahoo!ニュース、Googleニュースなど
- ニュース系ポータルサイト: livedoorニュース、グノシーなど
- 専門性の高いニュースサイト: ITmedia、TechCrunchなど
- エンタメニュースサイト: モデルプレス、ナタリーなど
- まとめサイト: まとめサイト系ニュースなど
これのサイトは、一企業のブランディングやCV獲得が目的ではなく、話題性や時事性によるPV数確保が最優となりやすい媒体です。ビジネスモデルとしては、不特定多数向けの自動広告が収益源となるなど、従来のマスマーケティング媒体に近しいと言えるでしょう。
運営しているサイトがいわゆる「バイラルメディア」は、このイシューに最優先に取り組むべきでしょう。
また、事業者のマーケティング戦略や選定した集客チャネルの性質によっては、時事性・話題性がイシューとなる場合があります。
たとえば、SNSやTikTokといったプラットフォームでは、時事性や話題性に富んだコンテンツが拡散されやすい傾向にあります。方法論としては「Twitter(現:X)のトレンドで急上昇したワードに言及する」ことで、短期間で大きな注目を集め、フォロワー獲得を行うことができます。
また、昨今では「UGC(User Generated Content-ユーザー生成コンテンツ)」が重視されることも増えました。
ユーザーに自発的に事業者の利益になるコンテンツ生成を行ってもらうために、話題性のあるコンテンツを提供してSNS上での言及を増やす…という方法が有効です。
そのためには、事業者本人や広報担当者が自らのキャラクター性を売り出してユーザーとのコミュニケーションを積極的に行うこともありますし、自社プロダクトを利用しているインフルエンサーやYouTuberに企業案件を依頼してアンバサダー活動を行ってもらうケースも近年では増えています。
話題性や時事性をイシューとして扱う場合、その瞬間のトレンドやニュースにどれだけ素早く反応できるかが成功の鍵となります。タイムリーなコンテンツを提供することで、一時的にアクセス数を大幅に増加させたり、自社名やプロダクト名を知ってもらう機会を増やすことが可能となります。
WEBサイトの中でも、とくにブログやYouTubeといったコンテンツマーケティングに注力するのであれば、露出・集客手段の一つとして「時事性・話題性のあるコンテンツか?」というイシューを設定しておく選択肢も考えられます。
以下、追記予定項目
アクセス数の推移や読者の反応次第で、下記の見出し項目を追加予定です。
1-5.【ヒント】トリプルメディアから自サイトの位置付けを俯瞰する
2.設定したイシューからサイト設計を行う
2-1.ブランディング起点の場合
2-2.集客チャネル起点の場合
2-3.CV獲得起点の場合
2-4.話題性・時事性起点の場合
まとめ:サイト設計の”ブレない軸”を見つけ出すことが大事
以上のように、WEBサイトを制作・運用するにあたって、マーケティング視点で考えなければならないことが膨大にあります。
しかし、すべての要素にベストアンサーを出すのは現実的ではありません。
そのため「最重要なイシューは何か?」を見極めなければならないのです。
ブランディングに労力をかける余裕がなく顧客ニーズも見えていないならCV獲得を優先するべきですし、CV獲得せずとも事業が回っているならブランディングにじっくり時間をかけて市場に伝えるメッセージを洗練させるべきでしょう。
こうした「問い」と向き合わず、ただ手法や方法論のみが先行したマーケティング施策は、短期的に成果が出たとしても、いずれは行き詰まる運命になります。
サイト設計やコンテンツ戦略を考える際には、まず「どんな価値を提供するのか」「誰に向けて発信しているのか」という基本的な問いに立ち返る必要があります。あるいは「それを問う以前にまずは集客優先でデータ・経験を蓄積させるべきではないか?」という判断も、もちろん存在します。
こうした本質的な問いに答えを出すために各種フレームワークや思考法が存在すると理解すれば、自ずと使い方も見えてくるでしょう。
また、マーケティングの喫緊の課題となりやすい「費用対効果を下げる」といった問題も、本質的なイシューを特定しておくことでゆくゆくは達成可能です。
本ブログ「マーケミー」では、こうした「Insight Pleasure~まだ見ぬ洞察と出会う~」ことをミッションに掲げ、筆者が実体験を通して得た”他では得られないマーケティング知見や独自の洞察”を公開していきます。