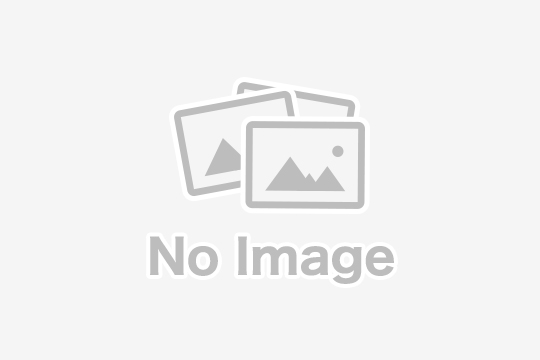マーケティング理論説明で初めのほうに出てくることが多い「3C分析」ですが、正しく使えている人が少ないことはご存知でしょうか?
ちまたのオウンドメディアを見ても、いかにも「教科書を見てまとめて説明しました」という記事ばかりで「本当に実務で活かせてるの?」と疑問が浮かぶばかりです。
実際、多くのフレームワークは「プレゼン用途に資料にそれらしくキレイにまとめられているだけ」であって、競合差別化など真のマーケティング戦略や実務に結びつけられてない場面によく出くわします。
そこでこの記事では、3C分析の正しい使い方を、私自身の実務経験からお伝えしていこうかと思います。
結論:3C分析は初期調査のための要素洗い出しに有効
結論ファーストで説明しますと3C分析は初期調査のための要素が洗い出しに有効です。
むしろこの用途以外で使うと無駄に思考したり、他のフレームワークに沿って考えれば済むことを3C分析でやろうとするなど判断ミスにつながる…というのが私の経験則です。
その理由について、下記「3C分析の主な利用シーン」としてお伝えしていきます。
利用シーン1.プロジェクト参加初期の調査
「初期調査」と聞くと、デスクトップリサーチや、人によってはリサーチ会社に頼むレベルのマーケティングリサーチを思い浮かべるかもしれませんが、そんな大層なものでもありません。
もっと粒度の低い「新しいプロジェクトに入ったタイミングでのキャッチアップのため」ぐらいに言い換えたほうがニュアンスとしては正しいかもしれません。
というのも、新規プロジェクトに入った段階で各種フレームワークなど内部資料が充実していたり、権限者から詳細な事業説明やマーケティング戦略の共有があればいいのですが、残念ながら私の経験では企業・クライアント側から詳細な説明が為されることは多くありませんでした。
加えて、マーケティング戦略に関する内部資料が充実しているということも、ほぼありません。
よって、新規プロジェクトの初期キャッチアップのためにも、3C分析埋められる程度の調査や聞き込みは自力で行わなければならない…という意味でも、3C分析の使い方は覚えておいて損はないというのが私の結論です。
利用シーン2.現状リソースと課題の正しい把握のため
ビジネスにおいては、頻繁に「物事を正しく把握できていない状態」が生じるものです。
たとえば「自分が顧客だと認識していたターゲットが、会社側が想定していたターゲットとズレていた」といった状態です。
より詳しく言うなら「自分はBtoCの顧客をイメージしていたが、企業側はBtoBの顧客をイメージしていた」といった状態だと、その後の業務でもすれ違いが生じてプロジェクト失敗要因となります。
そうしたすれ違いを防ぐ意味で、3C分析の主な役割は「現状把握」となります。
2.プロジェクトメンバーの認識レベル把握
現状把握と言っても様々な解釈があるでしょうが、より掘り下げて言うなら「自分の認識に見落としがないか?」「他のメンバーから共有されてない情報が多くないか?」といった自分の認識漏れやメンバーとの情報非対称性の発生状態を把握するためにも使えます。
極論、自分一人で完結できるプロジェクトならフレームワークなど必要ないと言えます。
なぜなら自分の頭でフレームワーク同等の処理ができていればわざわざ可視化する必要はないからです。
しかし、複数の利害関係者が存在し、マーケティング戦略を伝達して実行してもらうには、フレームワークを通してのコミュニケーションが不可欠です。
たとえば、
- プロジェクトメンバーがどれだけ3Cの要素を言語化できるか?
- 自分の考えにない3C要素が他メンバーの中に存在しないか?
- 関わるプロジェクトの自社リソースを正しく把握できているか?
といった使い方で各者の認識確認などには使えるでしょう。
とくに私の場合、実質的にチームメンバーのマネジメントや、経営階級の戦略を言語化・可視化する役割を求められることが年々増えているため、自分内で完結するだけでなく「フレームワークを通してメンバーに伝達できるか?」を主眼に考える必要が出てきています。
3.他のフレームワーク作成に繋げるため
3C分析は初期調査が主な活用法で、要素を洗い出したら他のフレームワークにつなげて使います。
これは、後ほど説明しますが3C分析の区分がざっくりし過ぎていて粒度が粗いためです。
ですので「自社についてこれぐらい理解している/していない」「顧客のイメージがおおよそこのぐらい」の確認意図で用いる程度で十分でしょう。
つまりは、3C分析の段階で「この粒度なら次はこのフレームワークが必要」と判断するための初期調査としても、3C分析をたたき台にするわけです。
3C分析を使う際のポイント
マーケティングで実務でフレームワークを用いて他者に戦略を伝えることが増えました。
しかし、それぞれのフレームワークには他メディアに記載されてないメリット・デメリットがあります。
ここでは、実際のマーケティングフレームワークを実務活かしてきた私の経験に基づく3C分析を使い際のポイントをご紹介していきます。
各要素の具体/解像度はバラけていてOK
他のマーケティング会社の記事を見ると「3C分析の目的は市場における成功要因を特定して自社の競争優位性を構築すること *出典」といった主張がありますが、私の経験則としては3C段階ではそこまで深く考えずに思いついたものをとりあえず記入するだけでOKという結論に至ってます。
その理由は、下記の2点となります。
- 3C分析の区分自体がざっくりし過ぎ
- 明確な目的があるなら別のフレームワークを使えばいいだけ
3C分析の区分自体がざっくりし過ぎ
第一に3Cの「Customer/Competitor/Company」の区分自体がざっくりし過ぎているので、この観点からして論点や構造の整理には向かないフレームワークだと言えます。
とくに「Customer」は「市場・顧客」と日本語訳されるため、マクロな市場とミクロな顧客が混同されるなどの問題もあり、整理するよりはアイデア発散向けのフレームワークだと考えるのが順当でしょう。
競合にしても「業界単位か?会社単位か?プロダクトそのものか?サービスの訴求内容か?」と3C分析の評価軸では定まらない時点で、ざっくりと「競合だと言えそうなもの」を洗い出す粒度で使用するのが、無駄な論点で思考が右往左往せずに済むでしょう。
明確な目的があるなら別のフレームワークを使えばいいだけ
3C分析の目的ではよく「事業の成功要因を発見する」などと紹介されていますが、それはあくまで「3C分析など様々なフレームワークを正しく使って分析した結果」に過ぎず、3C分析単体はせいぜい「3Cの要素を洗い出す」程度にしか使えません。
明確に「これを決めたい」と目的があるなら、他のフレームワークを最初から使えば良いだけの話です。
たとえば、競合分析を深めたいならオーシャン分析、独自の強みを抽出したいならSWOT/クロスSWOT/USP/STPなどのフレームワークを使えば良いということになります。
実際、私がBrightのマーケター向けのスキルマップを作成した際にも「3C分析は不要」としてスキル項目から外したのにも、そういった背景があります。
結論として、3C分析単体では何も決められないので、3C分析に時間をかけるのは避けて他のフレームワークで分析を深めるべきでしょう。
3C分析単体では意志決定できない
意志決定ができないというのは「明確な答えが出せない」とも言い換えられます。
要は、3C分析だけではステークホルダーを動かすに足る、戦略や示唆が出せるレベルの分析はできないのです。
3C分析で「独自の優位性を見つけよう」「差別化ポイントを見つけよう」と思っても、3Cの要素だけでは自社の強みを見つけるのは難しいです。
たとえば、競合で「競合と思える業界や企業/プロダクト名」を羅列して、自社で「自社の強みと思われる資源やプロダクト機能」を挙げても、それぞれのCの解像度が異なるので詳細な分析は難しいでしょう。
最低でも「競合の強みと弱み」「自社の強みと弱み」まで粒度・階層を揃える必要があります。
仮にそこまで粒度を上げるなら「SWOTやオーシャン分析で良くない?」と思えるので、無理に3C分析記載の詳細度を上げるよりは、他のフレームワークに移行して意志決定につなげるほうがフレームワークに思考を縛られるリスクも下がります。